教室について
沿革

福井大学病態制御医学講座内科学(1)は、昭和55年4月福井医科大学第一期生入学と同時に内科学第一講座として開講しました。初代教授は、京都大学内科学第一講座講師から赴任した中村 徹先生です。福井医科大学内科学第一講座は、血液病学と循環器病学を担当すると計画され、血液学専攻の中村教授と、京都大学第三内科から赴任した循環器病学専攻の原 晃助教授の組み合わせで出発しました。開講以来、毎年数名の入局者が加わるようになり、講座の陣容が整っていきました。研究面では、造血器腫瘍、なかでも急性白血病の化学療法が教室の中心的研究課題でありました。もう一つの柱である循環器グループでは、虚血性心疾患における血管狭窄や攣縮、虚血解除における心筋回復についての基礎的・臨床的検討がなされました。また、痛風・高尿酸血症も重要な研究分野であり、今日広く用いられている高尿酸血症の病型分類は、中村教授の膨大な研究成果の一つです。大学院も設置され、博士課程への入学者も徐々に増え、平成2年に内科学第一講座での博士第一号が誕生しました。中村教授定年までの15年間における発表論文数は約450編、学会研究会の発表は約2,000回に達しました。臨床面では、昭和58年10月、附属病院が開院し、西病棟5階において第二内科との共用する形で、教官・医員計8名により、25床の入院診療と週2回の外来診療が始まりました。昭和61年には東病棟が完成し、病床数も51床となって無菌室も設置されました。当時の新設国立医科大学の使命の一つに、地域医療への貢献がありました。第一内科東病棟5階は「AMLとAMIはいかなる時でも受け入れる」をモットーに、難治性内科疾患診療の最前線としてフル稼働しました。平成7年3月、中村教授は定年退官しました。

平成7年8月より第二代教授、上田孝典先生が着任しました。上田先生は京都大学内科学第一講座の中村研究室で博士号を取得し、中村先生の福井医科大学着任に伴い、昭和58年4月助手として福井医科大学に赴任しました。上田先生は昭和61年に講師、平成4年に助教授となり、平成7年に中村教授退官後、内科学第一講座教授に就任しました。研究テーマは引き続き白血病の化学療法で、抗がん薬のがん細胞内薬理・薬物動態の解析、薬剤耐性の克服についての研究を精力的におこないました。たくさんの門下生が上田教授の指導のもと学位の仕事をまとめました。臨床面では、北陸造血器腫瘍研究会を取りまとめ、臨床薬理学的視点から急性骨髄性白血病を主とする造血器悪性腫瘍に対する独創的な臨床研究を推進しました。上田教授は附属病院での診療をさらに充実させただけでなく、県内の主要病院に常勤医師を派遣し地域医療に多大なる貢献をしています。上田教授時代にはいくつかの大きな出来事がありました。平成15年福井医科大学は旧福井大学と合併して福井大学医学部となり、内科学第一講座は病態制御医学講座内科学(1)となりました。さらに平成24年8月、循環器内科学講座が独立し、内科学(1)の担当診療分野は血液、腫瘍、感染症、膠原病となりました。また、平成26年10月には30年ぶりの新病棟が完成し、内科学(1)の病棟は旧東5階から北7階へ移転しました。このような中、上田教授は20年に亘り教室を主宰し、平成27年3月定年を迎えました。その間、病院長、学部長を併任し、令和元年4月1日より福井大学長に就任されました。6年の長きに亘り大学運営のかじ取りをなされ、令和7年3月ご退職なされました。
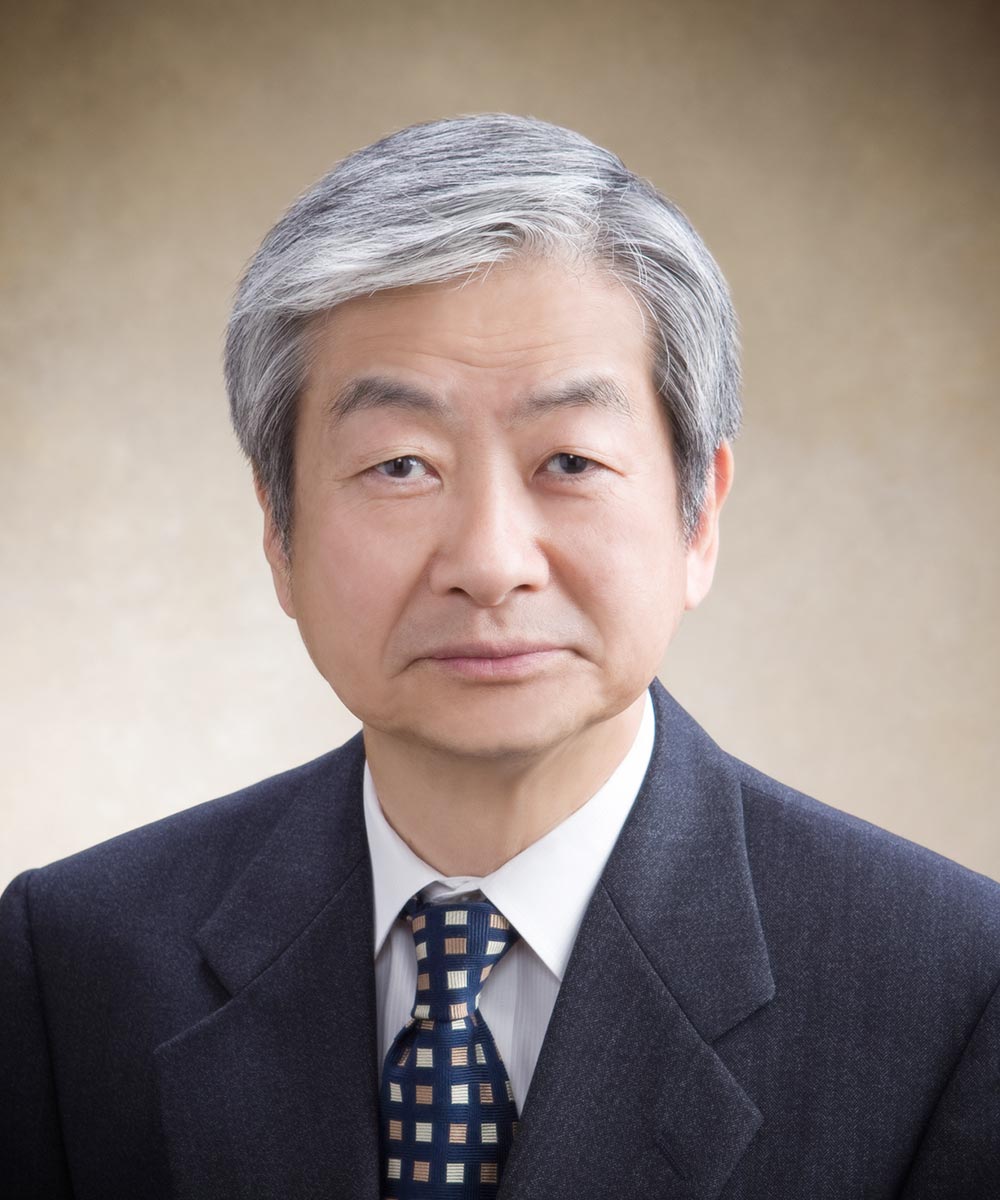
平成27年4月、山内高弘内科学(1)講師が第三代教授に就任しました。山内教授は中村教授、上田教授の系譜に連なり、抗腫瘍薬の臨床薬理、痛風・高尿酸血症を専門としました。基礎研究ではたくさんの新規薬剤の基礎検討を行い、新薬の耐性機序を解明し併用療法を考案しました。臨床研究では就任以来200件近い臨床試験を行い、2件の試験副委員長、1件の試験委員長を務め、50件を超える治験を行いました。さらには2度のAMED班長、ガイドライン作成委員(AML担当)、日本血液学会監事、日本成人白血病治療共同研究機構副理事長(JALSG)などを務めました。また、日本痛風・尿酸核酸学会副理事長にも就任しています。2026年2月に日本痛風・尿酸核酸学会総会長、2026年11月に日本臨床薬理学会学術集会長、2029年に国際プリン・ピリミジン代謝学会大会長を予定しています。
